2020.3.13
高崎映画祭プロデューサーから皆さまへ 志尾睦子
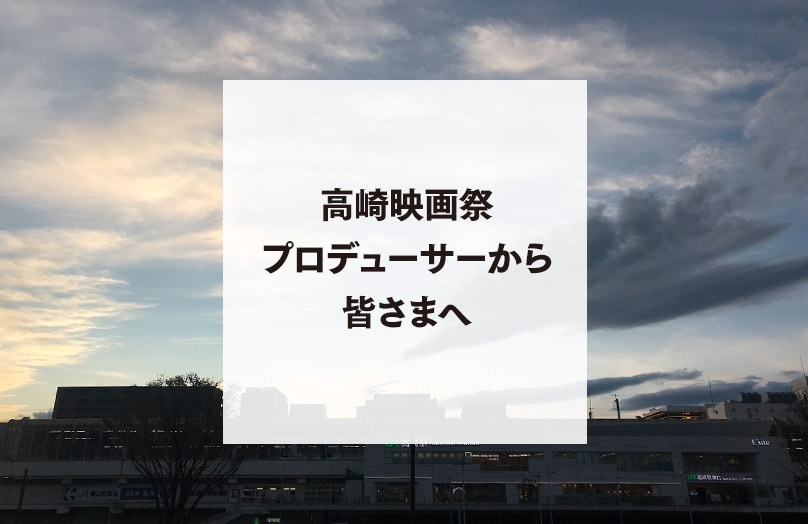
映画と共に時を刻む、春に寄せて
新型コロナウイルスに関する報道が連日される中、日々運営していく映画館の事を考え、日に日に迫る高崎映画祭の開幕に向けて状況を照らしながら、不安の隠せない日々を過ごしてきました。そんな中だからこそ、平穏に暮らすことの大切さをより意識して過ごすようにもなりました。むやみに慌てない。怖がらない。そのために、正しい知識を入れ、自分で予防に励み、他の人に優しくあることが大切です。
私は映画館主であり、映画祭プロデューサーである。その場に来ていただく方々に良き環境を提供できることが務めであり、何より映画の灯を消さないという大事な役目を担っています。この二つは、両輪です。おかげさまでシネマテークたかさきでは、志を同じくするスタッフが映画館環境を整え、お客様に映画を届け続けることができています。そして間近に迫る高崎映画祭でも同様に、全ての上映に対して何ができるかを考えてきました。
現時点での結論として、高崎映画祭委員会では第34回高崎映画祭の全上映プログラムの中止を決定しました。私はこれを最善の決定だと思っています。
数日間この事を協議する中で、ふと浮かんできた映画があります。中村義洋監督作品『フィッシュストーリー』(2009)です。
この映画が頭から離れなかった私は、委員会で全プログラム上映中止の決定が出た夜、一人部屋の中でゆっくりと『フィッシュストーリー』に身を委ねました。
2012年、彗星が地球に衝突する5時間前。人類滅亡の危機に際し、街から人は消え、荒れ放題となった商店街。そこを電動車椅子でうろつく男は、誰もいないはずの街の一角にレコード屋が開いているのを見つけ、入っていく。
店主「いらっしゃい」
男「いらっしゃいって。なんで、店、開けてるの?」
店主「…。レコード屋ですから。」
男「客なんか、来ないでしょ。」
その時奥から常連客らしき青年が現れる。
店主はパンク好きの青年に37年前の日本のパンクバンド逆鱗のレコードを聞かせる。この曲が世界を救うと言って。
数日間私の頭を支配していたのはこの冒頭シーンでした。店主を演じる大森南朋さんのぶっきらぼうな「いらっしゃい」が聞きたくて、こいつ何言ってんだよという呆れた感じで言う「…。レコード屋ですから。」を観たくて。
地球が滅亡する寸前まで、こうして一人映画館を開けていたい。この生き方は私の憧れでもありました。
そして高崎映画祭もまた、こんな姿勢で開催し続ける映画祭でありたい。
映画祭は映画館と違って、日常的なものではありません。年に一度のイベントでもある。その事をどう捉えて今何を判断していくのか、が大切だとこの数週間考えてきました。現時点では最善の選択をしたと思っていますが、感情論としては私にとって春のこの時期に高崎映画祭で上映ができないこと、お客様に今年のプログラムをご覧頂けないこと、は大きな喪失感でもありました。そんな中、『フィッシュストーリー』を観終えた今、また違った感覚が自分の中に生まれ始めてもいます。
『フィッシュストーリー』は伊坂幸太郎さんの同名小説を映画化したもので、4つの時代の全くバラバラの出来事が実は一つの曲で繋がっているというお話です。
お話の始まりは2012年で、軸となる曲が生まれたのは、その37年前の1975年。パンクバンド逆鱗は、デビューしたものの売れず、最後のレコーディング日を迎えます。彼らを見出し、彼らと共に音楽を作ったプロデューサーは、今は全く誰にも理解されない想いが、時空を超えて誰かにつながるかもしれない。だからこの曲は生まれた意味があると説きます。その後発売されたレコードは全く売れず、彼らは解散してしまう。語り継がれることもなくひっそりと。
それがどういった経緯で2012年につながるのか。中村監督の演出によって、人間の感情の起伏が画面に詰め込まれ、幾つものエピソードが収斂していく展開は爽快そのもので、ぽっかりと開いた私の心に新しい風が吹き抜けていきました。公開当時に観た時とまた違った感覚で映画が私の中で更に大きくなったと言うことだと思います。そしてあえて付け加えると、高崎映画祭では、この作品で正義の味方を演じた森山未來さんに最優秀助演男優賞を授与しました。過去の受賞者としては濱田岳さん、高良健吾さん、多部未華子さん、高橋真唯時代の岩井堂聖子さん、そして今年授賞の渋川清彦さんのご出演もあり、それぞれの皆さんとの時間も思い出すことになりました。山下敦弘監督のカメオ出演にニヤリとしたり、『ジャージの二人』でシネマテークたかさきに来てくださった中村監督との時間を思い出したりもしました。
そうして映画と自分の世界を行き来する中で、私はこの『フィッシュストーリー』に再びの勇気と教えをいただいた気がしました。映画を身近に感じると言うことはこう言うことなのだと。
2009年に公開されたこの映画が、2020年の3月、とある地方都市の映画祭プロデューサーの心をこうして慰めるとは、誰が想像したでしょうか。しかもそれは、自宅のテレビにネット配信の映画をつないで観ているわけです。『フィッシュストーリー』が描こうとしたことは、まさにこうしたことだったのではないだろうかと。
映画を届ける方法は、いくらでもある。今はそう思っています。たとえ、映画祭が開催中止になったとしても、それでも、高崎映画祭が皆さんに映画の素晴らしさをお伝えすることはできるわけです。
そう思いながら高崎の春を映画とともに私は今年も過ごしたいと思います。
高崎映画祭が皆さんにお届けできることも、また情報発信しながら続けてまいります。
映画がいつでもそれぞれの人生に寄り添ってくれますように。
その時間を大切にすごせますように。
そう願っています。
高崎映画祭
プロデューサー 志尾睦子
2020 春


